
手軽にかつ効率的に腹筋群を自宅で鍛えることのできるトレーニング器具がアブローラーや腹筋ローラーと呼ばれるものです。
そのタイプと目的別に適切な種類と選び方を解説するとともに、使い方についてもご紹介します。
腹筋ローラーが有効な筋肉部位
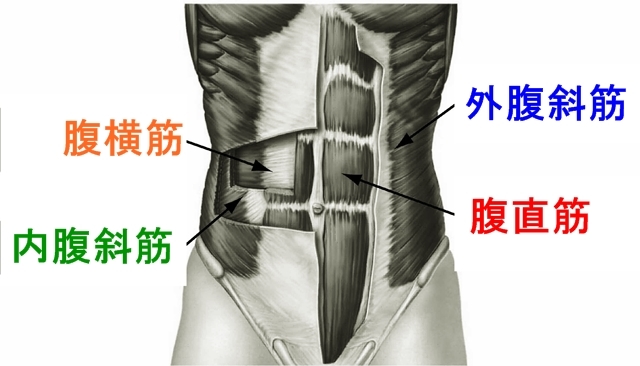
腹筋ローラーは腹筋群に有効です。腹筋群は表面から順に腹直筋・外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋の四層構造をしており、その主たる作用は以下のようになります。
腹直筋:体幹の屈曲
外腹斜筋:体幹の回旋
内腹斜筋:体幹の回旋補助
腹横筋:腹圧の維持
腹筋ローラーの種類
単輪タイプ

画像引用:Amazon
もっともスタンダートなタイプが単輪タイプです。安定性が少ないため、左右に傾くのを抑えながら動作することで、腹斜筋にも負荷が加わりやすいのが特徴です。
初心者にはやや制御が難しい部分があり、中級者向きのタイプと言えるでしょう。
二輪タイプ

画像引用:Amazon
二輪タイプは安定性が高く、初心者でも比較的容易に取り組めるのがメリットです。反面、横腹に対する負荷は低くなります。
三輪タイプ

画像引用:Amazon
運動が苦手な方は、さらに安定性の高い三輪タイプから始めることが推奨されます。
幅広タイプ

画像引用:Amazon
三輪タイプと同様に安定性が高く、なおかつ構造がシンプルなため比較的安価なのが、幅広タイプです。
下半身タイプ

画像引用:Amazon
通常の手で保持して使用する使い方のほか、足をかけて下半身主体でトレーニングできるのが下半身タイプです。下半身主体で動作を行うと、腹直筋のなかでも下部(下腹部)に負荷が集中しやすくなります。
腹筋ローラーの使い方
腹筋ローラーには以下のような使い方があり、それぞれの効果部位と特徴は以下のとおりです。
膝つき使用(膝コロ)
膝を床について行うバリエーションで、もっとも低強度で初心者向きのやり方です。
通常使用(立ちコロ)
つま先を床についてバリエーションで、もっともスタンダードなやり方です。膝コロができるようになったらチャレンジしたい、中級者向きのやり方です。
捻り使用(捻りコロ)
左右に軌道を変えながら行うバリエーションで、腹斜筋に負荷がかかります。膝をつくやり方やつま先だけをつくやり方などのバリエーションがあります。
これらのやり方の動画つき解説は下記の記事をご参照ください。






























