
ピラミッドセット法は筋肥大トレーニングとして有効なトレーニングセット法です。
その具体的な実施方法をコンパウンド種目(複合関節運動)とアイソレーション種目(単関節運動)それぞれから抜粋して例示解説します。
また、あわせてピラミッドセット法の派生バリエーションであるディセンディングセット法やドロップセット法についても解説していきます。
ピラミッドセット法の組み方

ピラミッドセットは中負荷→高負荷→中負荷と、使用重量をグラフにすると三角形になることから命名されています。
ピラミッドセット法の一般的な組み方例は、コンパウンド種目とアイソレーション種目それぞれで以下のようになります。
①ベンチプレスなどのコンパウンド種目
1セット目:最大筋力の60%×8レップ
2セット目:最大筋力の70%×6レップ
3セット目:最大筋力の80%×4レップ
4セット目:最大筋力の90%×2レップ
5セット目:最大筋力の70%×限界まで
6セット目:最大筋力の60%×限界まで
②バーベルカールなどのアイソレーション種目
1セット目:最大筋力の60%×8レップ
2セット目:最大筋力の70%×6レップ
3セット目:最大筋力の80%×4レップ
4セット目:最大筋力の70%×限界まで
5セット目:最大筋力の60%×限界まで
いずれの場合も、最大筋力の90%セットまでは予備疲労として実施し、最終2セットを最大筋力の70%と60%でオールアウトします。
※ピラミッドセット法にはさまざまな組み方があり、これは一例です。
なお、パワーリフティングの競技選手の場合などは、90%のセットの後に100%1レップのセットを組み込んで限界まで筋力向上を狙うこともあります。
▼詳細記事
https://sfphes.org/2019/10/pyramid-set.html
ピラミッドセット法の効果

ピラミッドセット法では6~8レップの中負荷トレーニングで筋繊維TYPE2aを、4レップの高負荷トレーニングで筋繊維TYPE2bを刺激できますので、筋肥大効果を主体にしながら筋力向上も狙うことが可能です。
筋繊維タイプの種類と特徴

筋力トレーニングを実施するにあたり、まず留意すべきことが、筋力トレーニングの実施目的に対して適切な負荷回数設定で行うことです。筋トレの対象となる骨格筋には主に3種類の筋繊維があり、それぞれに特性は異なります。その筋繊維特性とそれぞれに適切な負荷回数設定は次の通りです。
筋肥大を目的とした筋トレ
筋肥大を目的とした筋力トレーニングを実施する場合は、筋肥大しやすい特性を持つ「筋繊維タイプ2b(短時間に爆発的な収縮をする筋繊維)」を対象として行います。具体的には8~10回前後の反復動作で限界がくる負荷設定で筋力トレーニングを実施します。
体力作りを目的とした筋トレ
体力作りを目的とした筋力トレーニングを実施する場合は、中程度に筋肥大する特性を持つ「筋繊維タイプ2a(持久要素のある瞬発的な収縮をする筋繊維)」を対象として行います。具体的には12~15回前後の反復動作で限界がくる負荷設定で筋力トレーニングを実施します。
ダイエットを目的とした筋トレ
ダイエットを目的とした筋力トレーニングを実施する場合は、ほぼ筋肥大せずに緊密度が向上する特性を持つ「筋繊維タイプ1(持久的に収縮をする筋繊維)」を対象として行います。具体的には20回以上の反復動作で限界がくる負荷設定で筋力トレーニングを実施します。
厚生労働省による筋繊維に関する記載
骨格筋を構成している筋繊維には大きく分けて速筋と遅筋の2種類があります。速筋は白っぽいため白筋とも呼ばれます。収縮スピードが速く、瞬間的に大きな力を出すことができますが、長時間収縮を維持することができず張力が低下してしまいます。遅筋は赤みがかった色から赤筋とも呼ばれます。収縮のスピードは比較的遅く、大きな力を出すことはできませんが、疲れにくく長時間にわたって一定の張力を維持することができます。
引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-026.html
ディセンディングセット法とは
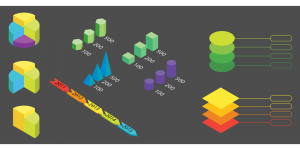
ピラミッドセット法の派生型のトレーニング方法としてディセンディングセット法があります。
このトレーニングセット法は、最大筋力の90%セット→80%セット→70%セット→60%セット→50%セットと、使用重量を下げながら全てのセットをオールアウトする方法です。
ピラミッドセット法よりも、さらに筋肥大向きのトレーニングセット法として知られています。
なお、ディセンディングセット法には、ピラミッドセット法のように重量を変更しながら1セットずつインターバルをはさんで実施するバリエーションと、1セットのなかで重量を落としながら実施するバリエーションがあり、後者をドロップセット法とも呼びます。
ドロップセット法の具体例
ベンチプレス80kg×10レップが限界と仮定した場合のディセンディングセット法の具体例は下記の通りです。
・1セット目
80kg×10レップ(限界まで)
・2セット目
80kg×7~8レップ(限界まで)
・3セット目
80kg×5~6レップ(限界まで)
(重量変更しインタバールなしですぐ)
50kg×4~5レップ(限界まで)
▼詳細記事
https://sfphes.org/2019/10/descending-set.html
さまざまなトレーニングセット法

さまざまなトレーニングセット法についての解説記事をまとめたものが下記の記事です。






























